
長州鍔の入念作にはやはり心奪われてしまう。隙の無い黒く澄んだ極精良な鉄地に絵画作品においての筆の強弱を使い分け描く様な、繊細且つ緻密な線細表現、高低差0,0mm程の中に、無限の広がりと奥深さが感じられ、これぞ日本が世界に誇る金工技術であり、激動の幕末に多数の名工を輩出した長州文化や歴史を感じられる名鍔である。
大きさ:(縦)8,0cm(横)7,53cm(重ね)0,4cm
附:特別保存刀装具鑑定書 Tokubetsu Hozon paper
価格:23万円 Price: 230,000 JPY
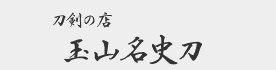
赤坂といえば武蔵野図や時雨亭図等が代表的で、赤坂派の図案構成や美意識を継承し、幕末まで様々に表現された作品があり、多様性を楽しむ刀装具文化としても、研究対象として興味深い。
伸びやかな線の重なりに三日月が特徴的な図案で、夜の清閑な時間を連想させ、心落ち着かせ、日本人の心に沁みわたる作品であり、状態も良い為、鉄味が艶やかで潤いすら感じる地鉄に形の良くバランスのとれたデザインが古典的であり、赤坂らしい典型作である。
大きさ:(縦)7,68cm(横)7,66cm(重ね)0,54cm
附:保存刀装具鑑定書 無銘 赤坂 Hozon paper Mumei Akasaka
価格:15万円 Price: 150,000 JPY
 手元を保護する目的の鍔という金具にも日本人は美意識や精神性を反映し、美術品に昇華した文化を現代の次の世代にも伝えていかなければ、と日々感じておりますが、この鍔も簡単には表現出来ない歴史や文化を孕んだ作品である。
手元を保護する目的の鍔という金具にも日本人は美意識や精神性を反映し、美術品に昇華した文化を現代の次の世代にも伝えていかなければ、と日々感じておりますが、この鍔も簡単には表現出来ない歴史や文化を孕んだ作品である。
まず古赤坂とは上三代の赤坂派の始祖達の作品を証するものであるが、この作品はとても特徴の表れた作品といえよう。 均等な美しい丸形では無く、少し上下に引っ張ったような不自然な丸形は時代や雅味を感じられ、後の時代の表現方法のような桐図では無く、どこか武骨で稚拙な桐紋は何故か心が落ち着く味を携え、勿論古赤坂としての切羽台、櫃穴の形状等は典型そのものであり、刀身に装着されてきた歴史も感じれる刀櫃穴の独特な形状も、また時代の特徴ともいえ、丸耳の形状もどこかゴツゴツとした景色が、また古赤坂の特徴として典型であり、この鍔一枚から日本金工史から刀装具文化を深く学べる作品として、名鍔である。
大きさ:(縦)7,59cm(横)6,88cm(重ね)切羽台 0,52cm 耳0,56cm
附:保存刀装具鑑定書 無銘 古赤坂 Hozon paper Mumei Ko-Akasaka
価格 ”売約” 致しました。 欧州 御人 有難う御座いました。
日本刀装金工史で京都三名工の一人であり、鉄地作品が特に評価高い鉄元堂正楽の作品である。 小振りではあるが、拡大鏡を使用し、その仕事の細部を拝見するとため息が出る程の圧巻の仕事振りで素晴らしい。
素材として一番加工しにくいといわれている精良な鍛鉄を使用してるが、木工作品の様に柔かく感じる程の超絶技巧の業はやはり名工と誉高い鉄元堂正楽の作品として後世に残し伝えるべき日本の文化財である。
龍の肉付、ウロコの精細さ、盛り上がっている力強い肩や背鰭の品格、勿論顔の細部や圧巻は宝珠を掴んだ爪が三次元のように複雑で、どのように鏨を入れたらこのような仕事が出来るのか、本当に素晴らしい
大きさ:(縦)6,11cm(横)5,8cm(重ね)切羽台 0,5cm
附:特別保存刀装具鑑定書 Tokubetsu Hozon paper
価格 ”売約” 致しました。 香川県 御人 いつも有難う御座います。
二代越後守包貞の長寸の覇気溢れた刀剣である。刀剣愛好家は一度は所有した事があるであろう、上々作の有名工で江戸期の刀剣文化を代表する刀工である。
大業物に分類し、特に晩年の助廣のような濤欄刃が有名であるが、この作品は完全な濤欄刃になる直前の作で、所々濤欄刃と丸月を焼き、個性的な箱刃や典型的な丁子刃と二代包貞の特徴が全て表れており、典型作且つ、代表作ともいえるだろう。 また長寸の地と刃は一点の緩みも無く、覇気堂々、美術刀剣としても典型な作といえる。
長さ:二尺五寸三分半 元幅3,15cm 先幅2,0cm 重ね0,8cm
附:特別保存刀剣鑑定書 白鞘入り
価格 ”売約” 致しました。 東京都 御人 いつも有難う御座います。
気持ちの良い京透の典型作で切羽台縦に伸ばしたような形状で刀櫃穴大きく、左右に張らない切羽台の形状は時代の上がる京透である事を証明しており、線の美しさの究極の美として京透に及ぶものはなく、この作品はそれである。また厚さも0,6mmの厚さでまた時代の上がる特徴であり、肉を極端に排除した軽量な設計、地透かす事により表面積の拡大を図り、強度を上げる透かし鍔の技術もまた力学的に実証されており、この鍔は線の細さを耳の赤銅覆輪により補強されており、京透鍔の名鍔である。
大きさ:(縦)7,96cm(横)7,85cm(重ね)0,59cm
附:保存刀装具鑑定書 無銘 京透 Hozon paper Mumei Kyosukashi
価格:18万円 Price: 180,000 JPY
見事に揃った作域の三所物で保存状態も頗る良く、金具使用感も少なくとても状態が良い。素晴らしく細かい赤銅魚子地は手擦れ感も全くなく、製作当時の状態を保った程の美しい仕上がりで、とても貴重である。
後藤家は古い添紋を使用し後代に仕立て直す作品も多く存在し、また古来より将軍家に刀装具製作を任された中、古後藤への研究と技術の継承がとても大事にされており、江戸期に入ると数多くの作品が古い作品からの創作や継承作が造られた。
この作品は寒山先生の箱書きには程乗作と極められており、後藤家のその当時のオリジナル三所物としてまた貴重で、元来は目貫は大小の作があったようで、大目貫は古後藤の大黒目貫が存在していた模様。 旧所有者と伝来の良さも伺える作品で貴重である。
目貫大きさ(左図)横2,9cm(右図)横2,98cm
附:特別保存刀装具鑑定書 無銘 後藤 Mumei Goto
価格:45万円 Price: 450,000 JPY